07.29

天下一品はなぜ店舗数を減らしているのか?その現状分析と未来戦略
こってりラーメンの代名詞として愛されてきた「天下一品」が近年、店舗数を減少させています。2025年6月末には首都圏で10店舗が一斉閉店するというショッキングなニュースが報じられ、多くのファンに衝撃を与えました。かつては「こってりといえば天下一品」と絶対的なポジションを確立していた老舗ブランドはなぜ縮小局面を迎えているのか?そしてこれからの天下一品は何をしていくべきなのか?本記事では、天下一品の現状を徹底分析し、ラーメン業界全体の変化も踏まえた未来戦略を探っていきます。

出典:飲食店ドットコム(https://www.inshokuten.com/foodist/article/7965/)
天下一品の大量閉店、その規模と現実
店舗減少の実態と数字で見る衝撃
2023年から2025年にかけて、天下一品の店舗数は着実に減少の一途をたどっています。まず、全国の店舗数推移を確認してみましょう:
- 2023年4月:223店舗
- 2024年4月:218店舗
- 2025年5月:209店舗
そして、2025年6月末には首都圏の10店舗が一斉閉店することが発表されました。これは首都圏全34店舗の約3割に相当し、この閉店により全国店舗数は200店程度にまで減少する見込みです。ピーク時には約240店舗あったことを考えると、わずか数年で2割近くが失われる計算になります。
特に衝撃的なのは、閉店対象となった店舗の立地です。渋谷店、新宿西口店、池袋西口店、目黒店、吉祥寺店、田町店、蒲田店、川崎店、大船店、大宮東口店といった、いずれも一等地や繁華街の中心部に位置する人気店舗が名を連ねています。通常、閉店するのは立地条件の悪い不採算店が中心になるものですが、今回はむしろ好立地の店舗が閉鎖されるという異例の事態となっています。

出典:テンポスフードメディア(https://www.tenpos.com/foodmedia/knowledge/know-promotion/41138/)
天下一品の店舗減少を引き起こした3つの主要因
天下一品の店舗減少には複数の要因が絡み合っていますが、特に大きな影響を与えている3つの要因を詳しく見ていきましょう。
1. フランチャイズ経営の課題とビジネスモデルの限界
天下一品の店舗の約9割はフランチャイズ方式で運営されており、今回閉店する店舗の多くもフランチャイジー(加盟店オーナー)が運営しているものです。実は、閉店の直接的な原因の一つは「フランチャイジーの離脱」にあります。
特に注目すべきは、「アトラスアンドカンパニー」や「エムピーキッチン」といった複数の天下一品店舗を運営していた会社が、天下一品からの撤退を決断している点です。例えば、エムピーキッチンは「三田製麺所」というつけ麺ブランドを展開しており、天下一品から三田製麺所への業態転換を進めています。
池袋東口店が三田製麺所に転換したケースに見られるように、これはフランチャイジーにとって極めて合理的な経営判断です。天下一品ブランドの価値が低下する中、以下のような比較検討が行われています:
- 収益性の比較:フランチャイズロイヤリティを払い続けるより、自社ブランドで柔軟な価格設定と差別化を行う方が収益性が高い
- 将来性の比較:「こってり」市場の成熟と競争激化が続く中、つけ麺市場にはまだ成長余地がある
- 運営の柔軟性:キャッシュレス対応や店舗デザインなど、現代的なニーズに合わせた柔軟な運営ができる
この「天下一品からの離脱」という現象は、単なる個別企業の意思決定ではなく、天下一品のブランド価値そのものに対する市場の評価を反映しています。
2. 「こってり」の独自性喪失と想起力の低下
かつて天下一品は、「こってり」という独特なカテゴリーを創造し、長期間にわたって独占的地位を築いてきました。「こってり=天下一品」という等式が消費者の頭の中に強固に結びついていたのです。これはマーケティング理論でいう「第一想起率(Top of Mind)」という、ブランド運営において極めて重要な指標でした。
しかし、時代の変化とともに、この「こってり=天下一品」の方程式が崩れ始めます:
- 2000年代後半〜2010年代:「こってり」系ラーメンを提供する店舗が急速に増加。「こってり=天下一品」から「こってり=複数の選択肢」へと消費者の認知構造が変化。
- 2010年代後半〜現在:「こってり」という特徴自体が標準化され、多くの店舗が似たような濃厚スープを提供するようになった。特に家系ラーメン店の急増により、「こってり」は特別な体験ではなく当たり前の選択肢に。
この「想起力の低下」は、具体的に以下のような経営面での悪影響をもたらしています:
- 顧客獲得コストの増加:かつては「こってりが食べたい」という需要が自動的に天下一品への来店につながっていたが、現在では広告やプロモーションによる積極的な集客が必要に
- 客単価向上の困難:競合が増え、価格競争に巻き込まれることで価格プレミアムを維持できない
- リピート率の低下:顧客は様々な「こってり」系ラーメンを試すようになり、天下一品固定客が減少
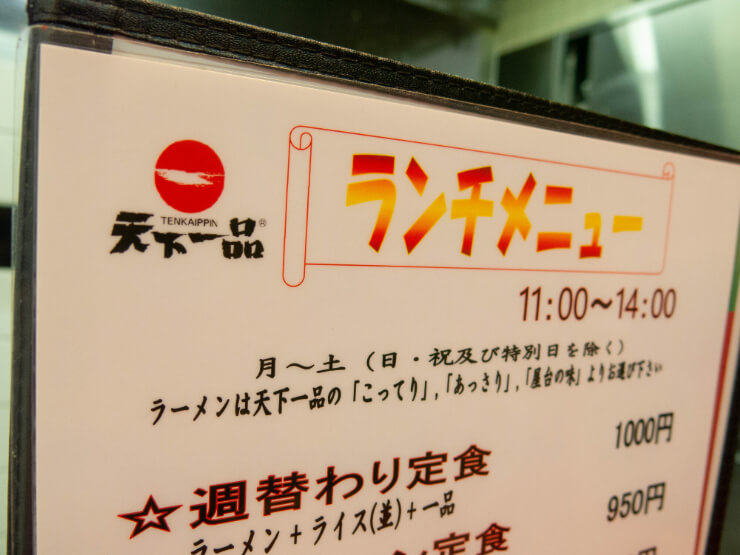
出典:テンポスフードメディア(https://www.tenpos.com/foodmedia/knowledge/know-promotion/41138/)
3. ラーメン業界の構造的課題と消費者ニーズの変化
天下一品が直面している問題は、同社固有のものだけではありません。ラーメン業界全体が厳しい構造的課題に直面しており、それが天下一品の店舗減少に拍車をかけています。
「1000円の壁」という価格設定の呪縛
ラーメン業界には「1000円の壁」と呼ばれる特有の事情があります。消費者が1杯1,000円を超えるラーメンに強い抵抗感を持つため、他業界に比べて値上げが極めて困難という構造的な課題です。
この状況下で原材料費や人件費の高騰が直撃し、利益率を圧迫。帝国データバンクの調査によると、ラーメン原価は2年前から1割増と試算されていますが、「1000円の壁」により、コスト増を価格に転嫁できないことが、多くのラーメン店の経営を圧迫しています。
過当競争とラーメン業界の倒産増加
ラーメン業界の市場環境は非常に厳しさを増しています。帝国データバンクによると、2024年のラーメン店経営事業者の倒産は72件と過去最多を更新しました。この背景には以下の要因があります:
- 市場の飽和と新規参入の継続:国内に2万店以上のラーメン店が存在し、毎年約3,000店舗以上の新規開業が続く
- 限られたパイの奪い合い:需要が頭打ちの中での競争激化
- 新業態への客離れ:様々な飲食業態との競争
健康志向の高まりと「こってり」への逆風
消費者の健康意識の高まりも、「こってり」を看板に掲げる天下一品には逆風となっています。
- 低カロリー・低脂質志向:若い世代を中心に、脂っこい食事を避ける傾向
- ヴィーガンラーメンなどの台頭:植物由来の材料を使用した罪悪感なく食べられるラーメンの人気上昇
- 多様な健康系ラーメン:サラダ感覚で食べられる野菜たっぷりのラーメンなど
このような消費者ニーズの変化に対応しきれなかったことも、天下一品の店舗減少の一因となっています。
天下一品はこれから何をすべきか?再生のための戦略提言
天下一品が直面している問題は深刻ですが、適切な戦略により回復の可能性は十分にあります。ここからは、天下一品が取るべき戦略と具体的なアクションプランを提言します。
1. カテゴリー再定義による差別化戦略
「こってり」というカテゴリーが標準化され、コモディティ化している今、天下一品にとって重要なのは、新たなカテゴリーの創造です。
戦略のポイント:「こってり」から一歩進んだ、新しいカテゴリーを創造し、そのカテゴリーでの第一想起を獲得する。
具体的なアクション:
- 天下一品独自の価値提案を再定義する:「伝統的な職人技法による本格こってり」「47年の歴史に裏打ちされた唯一無二のこってり」など、歴史と伝統という競合が容易に模倣できない要素を前面に出す
- 新しいサブカテゴリーの確立:「プレミアムこってり」「職人こってり」「元祖こってり」など、格上感を演出し、そこでの第一想起を獲得する
- ブランドストーリーの可視化:創業からの歴史や職人の技術など、ストーリー性のあるコンテンツを積極的に発信
2. 顧客体験価値の向上と「天下一品体験」の創造
商品そのものでの差別化が困難な今、顧客体験全体での差別化が重要です。単なるラーメン店ではなく、「天下一品でしか得られない特別な体験」を提供する戦略を展開します。
戦略のポイント:「食事」から「体験」へのシフト。来店客に「ただラーメンを食べた」ではなく、「特別な天下一品体験をした」と感じてもらうこと。
具体的なアクション:
- 店舗デザインの刷新:天下一品の歴史やこだわりを感じられる空間づくり
- 接客スタイルの進化:こってりの作り方や歴史について説明できるスタッフの育成
- 限定メニューやシーズナルメニューの拡充:「今しか、ここでしか食べられない」という特別感の演出
- 天下一品のブランドの象徴となるような新しいビジュアルアイデンティティの構築

出典:ITmedia(https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2505/28/news034.html)
3. デジタル戦略とテクノロジー活用の本格化
天下一品は多くの店舗でキャッシュレス決済に対応していないなど、デジタル面での対応の遅れが指摘されています。これからのラーメン業界で生き残るためには、デジタル戦略の強化が必須です。
戦略のポイント:現代の消費者行動に合わせたデジタル体験の構築と、テクノロジー活用による業務効率化。
具体的なアクション:
- 全店舗でのキャッシュレス決済対応の加速
- 公式アプリの開発:ロイヤルティプログラム、来店履歴に応じた特典、こってりレベルのカスタマイズ機能など
- SNSマーケティングの強化:Instagram、TikTokなどでの若年層向けコンテンツ発信
- オンライン注文・デリバリーサービスの導入
- デジタルサイネージやタッチパネル注文システムの導入による待ち時間短縮
4. 健康志向に対応した新メニュー開発
消費者の健康意識の高まりに対応するため、従来の「こってり」の良さを活かしつつ、健康志向にも配慮したメニュー開発が必要です。
戦略のポイント:「健康×こってり」という一見矛盾する要素の両立を図る。
具体的なアクション:
- 低カロリー版こってりの開発:同じ濃厚な味わいを保ちつつ、カロリーや脂質を抑えたメニュー
- 野菜たっぷりこってりの開発:栄養バランスを考慮したメニュー構成
- ハーフサイズメニューの導入:少量でも満足感のある提供方法
- 植物性代替油の研究:動物性油脂の一部を植物由来の健康的な油に置き換える試み
- 季節限定の健康メニュー:旬の野菜を取り入れた限定こってりなど
5. フランチャイズモデルの抜本的改革
フランチャイジーの離脱を防ぎ、パートナーシップを強化するためには、フランチャイズモデル自体の見直しが必要です。
戦略のポイント:単なるブランド使用権の提供ではなく、成功のためのトータルソリューションを提供する。
具体的なアクション:
- データ分析支援の強化:各店舗の売上データ、顧客データ、競合店情報などを統合的に分析し、個別店舗に最適化された経営アドバイスを提供
- マーケティング支援の充実:地域特性に合わせた効果的なプロモーション戦略の提供
- 技術支援の強化:最新の調理技術や効率化ノウハウの共有
- フランチャイズ契約の柔軟化:成果に応じたロイヤリティ体系の導入など
- フランチャイジー間の横のつながりを強化し、ベストプラクティスの共有を促進
革新的事例:滋賀県高島市今津町の「天下一品 近江今津店セルフ」モデル
天下一品は2024年7月、滋賀県高島市今津町に「天下一品 近江今津店セルフ」という革新的な業態をオープンさせました。これは天下一品初のセルフ方式の店舗で、従来の店舗とは一線を画する新しいビジネスモデルを導入しています。
この店舗の特徴は以下の通りです:
- お客様自身がトッピングや薬味を調整できるセルフスタイル
- 2025年6月からは画期的な「食べ放題」サービスを開始(ラーメン1杯を注文すると30分間サイドメニューが食べ放題になる)
- 人手不足という業界全体の課題に対応した効率的な運営モデル
- 目の前で「こってり」が作られる様子を見られる体験型の価値提供
- 家族連れにも嬉しい「未就学児は無料」という子育て支援策

出典:PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000152950.html)
このモデルは、従来の天下一品の強みである「こってり」の味を維持しながらも、時代のニーズに合わせた新しい体験価値を創出しています。また、人手不足という構造的課題に対応しつつ、顧客体験を向上させるという一石二鳥の効果をもたらしています。
今後のフランチャイズモデル改革への示唆:
この近江今津店セルフの成功事例を他の店舗にも展開することで、天下一品全体のフランチャイズモデルを刷新できる可能性があります。具体的には:
- 複数の店舗形態の提供:従来型の店舗に加え、セルフ型、食べ放題型、小型カウンター型など、立地や投資規模に合わせた複数の選択肢を用意
- 投資規模と収益性のバランス:セルフ方式による人件費削減と客単価維持の両立
- 新たな客層の開拓:家族連れや若年層など、これまで十分に取り込めていなかった層へのアプローチ
- 地域特性を活かした柔軟な運営:全国一律のモデルではなく、地域の特性や需要に合わせた柔軟なビジネスモデルの採用
この近江今津店セルフモデルは、天下一品が今後のフランチャイズ展開において一つの方向性を示す重要な実験と言えます。フランチャイジーにとっても、より魅力的で持続可能なビジネスモデルを提示することができれば、離脱を防ぎ、新たなオーナーの獲得にもつながるでしょう。
この革新的なアプローチこそが、天下一品のフランチャイズモデルを再構築し、新しい時代に適応していくための重要な一歩となります。
天下一品の未来展望:変革とチャレンジの時
これまで見てきたように、天下一品は店舗数減少という厳しい現実に直面していますが、ブランドの根本的な価値を見直し、時代のニーズに合わせた変革を実行することで、再び成長軌道に戻る可能性は十分にあります。
新たな出店戦略とターゲット市場の再定義
今後の天下一品は、単に店舗数の回復を目指すのではなく、質の高い成長を追求すべきです。具体的には以下のような取り組みが考えられます:
立地戦略の転換:
- 高コストの都心一等地から、生活圏に近い郊外型店舗への軸足移動
- 商業施設内への出店による新規客層の開拓
- オフィス街でのランチ需要に特化した小型店舗の展開
ターゲット層の拡大:
- これまでの中心顧客だった男性ビジネスパーソンや学生だけでなく、女性やファミリー層、シニア層へのアプローチ
- インバウンド観光客向けの「日本のこってり文化体験」としての店舗展開
- 健康志向の強い顧客層を取り込むための新メニュー開発
海外展開による新市場開拓
国内市場が成熟化する中、海外市場への展開も重要な成長戦略となります。「日本のこってり文化」としてのブランディングを強化し、以下の取り組みを進めることが考えられます:
- アジア圏を中心とした海外出店の加速
- 現地の食文化や嗜好に合わせたメニューのローカライズ
- 「日本の伝統的ラーメン」としてのブランドポジショニング
- 海外の食のトレンドを国内店舗にフィードバックする双方向の商品開発体制
ブランドレガシーを活かした新たな展開
47年の歴史を持つ天下一品には、多くのファンの思い出と強い愛着が詰まっています。このブランドレガシー(遺産)を活かした新たなビジネス展開も検討すべきです:
- 冷凍食品やインスタントラーメンなど、家庭で楽しめる商品ラインの強化
- こってりスープのボトリング販売やギフトセット展開
- 「天下一品博物館」のような体験型施設の開設
- 他ブランドとのコラボレーション商品の開発
デジタルトランスフォーメーションによる業務革新
フランチャイズチェーンとしての競争力を高めるためには、バックエンド業務の効率化も重要です:
- AIを活用した需要予測システムの導入
- サプライチェーン全体のデジタル化による原価管理の最適化
- ロボット技術の活用による人手不足対策
- データ分析による個店ごとの最適なメニュー構成の提案
まとめ:変革の時を迎えた天下一品
天下一品の店舗数減少は、単なる一企業の問題ではなく、ラーメン業界全体が直面する構造変化の象徴とも言えます。「こってりの王者」として確固たる地位を築いていた天下一品が、その独自性の喪失と市場環境の変化によって岐路に立たされているのです。
しかし、危機はしばしば変革の好機でもあります。天下一品が持つ47年の歴史とブランド資産、熱狂的なファン層、そして「こってり」という独自の文化は、決して小さくない競争優位性です。これらを活かしながら、時代のニーズに合わせた大胆な変革を実行することで、天下一品は再び成長軌道に乗ることができるでしょう。
今後も天下一品がどのような戦略を展開し、どのように変化していくのか、ラーメン業界の動向とともに注目していきたいと思います。
参考文献
[1] 日本ソフト販売, 「【2025年版】ラーメンチェーンの店舗数ランキング」, (2025年6月17日), https://www.nipponsoft.co.jp/blog/analysis/chain-ramen2025/
[2] 東洋経済オンライン, 「天一が大量閉店…逆に増えてるチェーンには《意外な共通点》が」, (2025年7月10日), https://toyokeizai.net/articles/-/889368?display=b
[3] テンポスフードメディア, 「「天下一品」の閉店ラッシュが続く!?その要因について徹底解説!」, (2025年7月17日), https://www.tenpos.com/foodmedia/knowledge/know-promotion/41138/
[4] マーケティングアナリティクスサイト, 「「天下一品」首都圏大量閉店から読み解く: 老舗ブランドが陥ったカテゴリーの罠」, (2025年6月26日), https://marketing-analytics.site/tenkaippin/
[5] ITmedia, 「「天下一品」閉店の背景は? 唯一無二の”こってり”に陰りが見える理由」, (2025年5月28日), https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2505/28/news034.html
[6] note, 「もう無理…」閉店ラッシュ止まらず!”こってり最後の砦”天下一品に何が起きている?」, (2025年5月16日), https://note.com/jk1007kd/n/n59e15d521427
[7] KICKS Blog, 「「天下一品」の大量閉店、その裏にあった弟子の独立戦略」, (2025年6月29日), https://kicks-blog.com/entry/2025/06/29/103946
[8] how-seniors-work, 「天下一品の今後が不安?首都圏閉店と全国推移から読み解く未来図」, (2025年5月16日), https://how-seniors-work.hatenablog.com/entry/2025/05/16/182552
[9] 飲食店ドットコム, 「ラーメンチェーン『天下一品』、首都圏で閉店ラッシュ。原因はフランチャイズ離れか?」, (2025年6月17日), https://www.inshokuten.com/foodist/article/7965/
[10] マイ女子食品, 「2025年のラーメン業界はどうなる?最新のフードトレンドから予測する未来」, (2025年3月), https://www.myojousa.com/ja/blog/ramen-trends-2025/
[11] 国丸ラーメン, 「醤油からとんこつまで!ラーメン専門家が教える2025年のラーメントレンド」, (2025年3月6日), https://kunimaru.net/2025/03/06/results/ramen-2025-trend/
[12] 日本食糧新聞, 「ラーメンの最新事情:二極化進むラーメン市場、無添加ブームが到来」, (2024年), https://news.nissyoku.co.jp/restaurant/grs-293-0006
[13] 帝国データバンク, 「「ラーメン店」の倒産動向」, (2025年1月), https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/o5qvdhnmmzu/
[14] ゆいマーケ, 「天下一品:唯一無二のこってりラーメンが挑む」, (2024年12月28日), https://yui-marke.com/article/3361/
[15] テンポスフードメディア, 「再ブームに期待大!スープの濃厚さやコクが効いた「背脂ラーメン」の秘密に迫る!」, (2025年), https://www.tenpos.com/foodmedia/newstrend/33851/
天下一品, ラーメンチェーン, こってりラーメン, 店舗閉店, フランチャイズ, ブランド戦略, ラーメン業界, 健康志向, デジタル戦略, 顧客体験, マーケティング, 飲食店経営, ブランド再構築, キャッシュレス決済, 海外展開
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




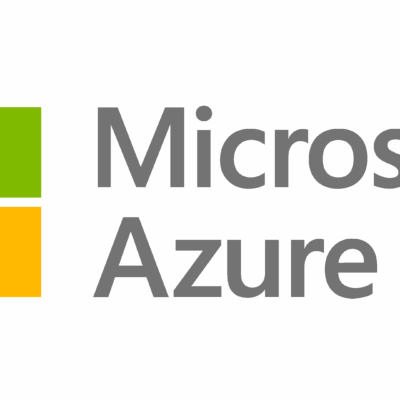
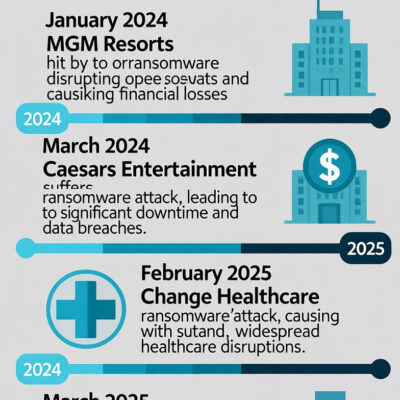





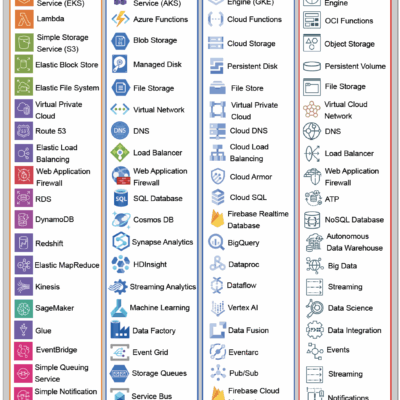
この記事へのコメントはありません。