08.02

区民負担3万円増の衝撃!東京23区の民間火葬場が区民葬儀取り扱い中止を決定 その背景と解決策を徹底解説
東京23区で暮らす住民にとって、葬儀費用の負担軽減は重要な公共サービスです。しかし2025年8月1日、区民の生活を支えてきた制度に大きな変化が発表されました。この記事では、なぜこのような事態に至ったのか、そして今後私たちはどう対応すべきかを詳しく解説します。
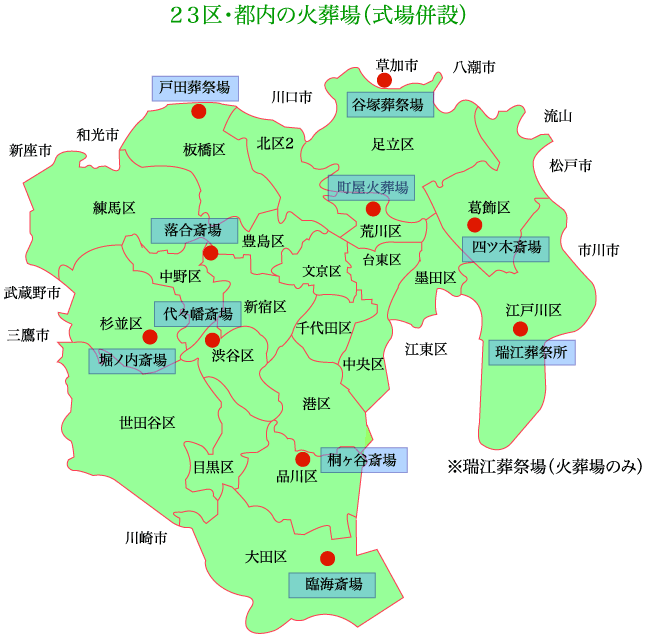
出典:安心価格のいい葬儀(https://www.e-sougi.jp/kasouba/kasouba-map.html)
突然の発表:区民葬儀制度から撤退する東京博善の決断
2025年8月1日、広済堂ホールディングスの子会社である東京博善株式会社が、2026年3月31日をもって東京23区の区民葬儀制度から撤退すると発表しました。この発表は、多くの区民にとって寝耳に水の出来事でした。
東京博善は、東京23区内にある民間火葬場7箇所のうち6箇所を運営しており、事実上の寡占状態にある企業です。同社が運営するのは以下の火葬場です。
- 町屋斎場(荒川区)
- 四ツ木斎場(葛飾区)
- 桐ケ谷斎場(品川区)
- 幡ヶ谷斎場(渋谷区)
- 落合斎場(新宿区)
- 堀ノ内斎場(杉並区)
これらの施設では、これまで区民葬儀制度を利用することで、通常90,000円の火葬料が59,600円で利用できていました。その差額30,400円は東京博善が負担していたのです。

出典:東京博善公式サイト(https://www.tokyohakuzen.co.jp/)
区民葬儀制度とは何か:戦後復興期に生まれた支援制度
区民葬儀制度について理解するためには、その歴史的背景を知る必要があります。この制度は、戦後間もない1947年頃、都民の生活が困窮していた時代に「都民葬儀」として始まりました。
制度創設の経緯
戦後復興期、多くの市民が経済的困窮に直面していました。特に葬儀費用は家族にとって大きな負担となっており、適切な弔いを行うことが困難な状況が頻発していました。このような社会情勢を受け、葬祭業協同組合が東京都に働きかけ、低所得者でも尊厳ある葬儀を行えるよう「都民葬儀」制度が創設されました。
制度の変遷
1947年:「都民葬儀」として制度開始
1965年:各区への移管により「区民葬儀」として現在の形に発展
1994年:東京博善が広済堂の子会社化、民営企業による運営本格化
この制度では、対象となる区民に対して「祭壇・搬送・火葬」がセットになった葬儀券を交付し、通常よりも大幅に安価な料金で葬儀を執り行うことができました。特に火葬料金については、民間火葬場の協力により大幅な減額が実現されていたのです。
東京23区の特殊な火葬場事情:なぜ民間企業が運営するのか
東京23区の火葬場運営体制は、全国的にみても極めて特殊な状況にあります。全国では多くの自治体が直営または公社による火葬場運営を行っているのに対し、東京23区では9箇所の火葬場のうち7箇所が民間企業による運営となっています。
歴史的経緯:明治時代からの民間運営
この特殊な状況は、明治時代からの歴史的経緯に起因します。江戸時代から続く荼毘所(だびしょ)の伝統があり、明治期の近代化の過程で現在の火葬場の多くが民間によって設立されました。これは、1948年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」より前の時代の話です。
同法第10条では、墓地や火葬場の経営主体を「地方公共団体」を原則とし、「その他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるもの」と規定していますが、既存施設については「みなし許可」として継続運営が認められていました。
現在の運営状況
公営火葬場(2箇所)
- 臨海斎場(大田区):火葬料金44,000円
- 代々幡斎場(渋谷区):火葬料金59,600円
民営火葬場(7箇所)
- 東京博善運営(6箇所):火葬料金90,000円(2024年6月より)
- 戸田葬祭場(1箇所):火葬料金80,000円
この状況により、東京博善は23区内の火葬需要の約7割を担っており、事実上の寡占状態となっています。
火葬料金高騰の実態:全国平均との驚くべき格差
東京23区の火葬料金の高さは、全国的にみても異常な水準にあります。日本経済新聞の調査によると、全国88都市の火葬料金平均は10,054円であり、無料の自治体も多数存在します。一方、東京23区では最高90,000円と、全国平均の約9倍という驚くべき格差が生じています。
東京博善の火葬料金推移
東京博善の火葬料金の変遷を見ると、特に近年の急激な値上げが顕著です。
料金推移
- 2020年:59,000円
- 2021年1月:75,000円(16,000円値上げ)
- 2022年6月:燃料サーチャージ制導入(月変動制)
- 2024年6月:90,000円(定額制に変更)
わずか4年間で火葬料金が約1.5倍に急騰したことになります。この値上げの理由として東京博善は「燃料費の高騰」を挙げていますが、他地域の火葬場と比較すると説明のつかない水準の高さとなっています。
全国主要都市との比較
主要都市の火葬料金(2024年)
- 横浜市:12,000円
- 大阪市:9,000円
- 名古屋市:7,000円
- 福岡市:6,000円
- 札幌市:無料
- 仙台市:6,000円
この数字を見ると、東京23区の火葬料金がいかに突出して高いかが分かります。特に札幌市のように無料で提供している自治体があることを考えると、90,000円という料金設定は市民生活への影響が深刻と言わざるを得ません。

出典:葬研(そうけん)(https://souken.info/tokyo-hakuzen-mondaiten/)
中国資本の参入と経営方針の変化
東京博善の運営方針に大きな変化をもたらした要因の一つが、広済堂ホールディングスの経営権の変動です。2019年、広済堂の創業者親族が株式を中国人実業家・羅怡文氏に売却しました。羅氏は家電免税店「ラオックス」の経営で知られる人物です。
経営体制の変遷
1994年:広済堂が東京博善を子会社化
2019年:創業者親族が羅怡文氏に株式を売却
2022年:羅氏のグループ企業が広済堂株の40%超を取得
経営方針の変化
中国資本の参入により、東京博善の経営方針に明確な変化が現れました。従来は半ば公共的な性格を重視していた運営から、より商業的な運営へとシフトしています。
具体的な変化
- 火葬料金の段階的値上げ
- 燃料サーチャージ制の導入
- 骨壺の独占的販売
- 僧侶控室の有料化
これらの変化は、火葬場の公共的性格よりも営利性を優先する姿勢を示しており、今回の区民葬儀制度からの撤退もこの流れの延長線上にあると考えられます。
東京博善の主張:制度の問題点と撤退理由
東京博善は、区民葬儀制度からの撤退理由として以下の点を挙げています。
制度の変質に対する指摘
同社は「本来生活困窮者の救済としての減額制度が、誰もが利用できる制度になっている」と指摘しています。確かに現在の区民葬儀制度は、所得制限などの厳格な適用基準がなく、多くの区民が利用可能な状態となっています。
企業負担の問題
火葬料金の通常価格90,000円と区民葬価格59,600円の差額30,400円を、東京博善が企業負担していることについて「時代に見合わない」と主張しています。年間の利用件数を考慮すると、この負担額は相当な規模になると推測されます。
制度見直しの必要性
東京博善は、昨年12月から特別区長会と制度の見直しについて協議を重ねてきたとしています。しかし、根本的な解決に至らず、最終的に制度からの撤退という決断に至りました。
区民生活への深刻な影響:3万円の負担増が意味するもの
東京博善の撤退により、区民は約30,000円の負担増を強いられることになります。この金額の影響を具体的に考えてみましょう。
家計への影響
葬儀費用は予期しない出費であり、多くの家庭にとって大きな負担となります。火葬料金だけで3万円の負担増となると、以下のような影響が予想されます。
低所得世帯への打撃
- 生活保護受給世帯:葬祭扶助の上限額との関係で深刻な影響
- 年金受給世帯:限られた収入での3万円負担は重い
- 若年世帯:突発的な出費への対応が困難
社会的弱者への影響
特に深刻なのは、もともと区民葬儀制度の恩恵を受けていた社会的弱者への影響です。制度創設時の目的であった「生活に苦しい方の負担軽減」が達成できなくなる可能性があります。
遺体火葬の拒否事例
既に一部では、火葬料金の高さを理由に遺族が火葬を拒むケースも報告されています。これは公衆衛生上の問題にもつながる深刻な事態です。
特別区長会の対応:緊急助成制度の創設
この事態を受けて、特別区長会は緊急的な対応策を検討しています。
23区共通助成制度の創設
特別区長会は、2026年度から「23区共通の助成制度」を創設することを決定しました。この制度の概要は以下の通りです。
対象者:特別区区民葬儀利用者のうち、特別区指定民営火葬場利用者
実施期間:令和8年度から当面の間
助成内容:詳細は2026年度予算編成過程で決定
根本的解決への取り組み
特別区長会は、この問題の根本的解決に向けて、国への要望も行っています。
厚生労働省への要望内容(2024年8月27日提出)
- 火葬場経営の永続性・非営利性の確保
- 民間火葬場の経営状況透明化
- 料金設定の適正化に関する法整備
これらの要望は、火葬場の公共的性格を重視し、適正な運営を求めるものです。
全国各地の火葬場運営:参考になる取り組み事例
東京23区の問題を解決するヒントとして、全国各地の火葬場運営事例を見てみましょう。
公営火葬場の運営モデル
横浜市の事例
- 運営主体:横浜市(直営)
- 火葬料金:12,000円
- 特徴:市民サービスの一環として位置づけ
札幌市の事例
- 運営主体:札幌市(直営)
- 火葬料金:無料
- 特徴:基本的な市民サービスとして提供
公設民営の運営モデル
大阪市の事例
- 運営主体:指定管理者制度
- 火葬料金:9,000円
- 特徴:公的管理下での効率的運営
これらの事例を見ると、公的関与により適正な料金水準を維持することが可能であることが分かります。
問題の根本原因:なぜこのような事態に至ったのか
今回の問題は、複数の要因が重なって生じたものです。
構造的要因
寡占市場の問題
東京博善が23区内火葬場の約7割を運営していることで、競争原理が働かない状況が生まれています。これにより、価格設定が市場メカニズムではなく、企業の一方的な判断に委ねられています。
法的規制の限界
現行の墓地埋葬法では、既存の民間火葬場に対する料金規制や経営内容への監督権限が限定的です。これにより、公共的サービスでありながら適切な規制が困難な状況となっています。
政策的要因
公的火葬場整備の遅れ
東京23区では、民間火葬場への依存度が高く、公的な代替施設の整備が進んでいません。これにより、民間企業の方針変更に対する対応力が不足しています。
制度設計の課題
区民葬儀制度は、民間企業の善意に依存する部分が大きく、企業側の方針変更に対する対応策が不十分でした。
今後の解決策:持続可能な火葬サービスに向けて
この問題を根本的に解決するためには、複数のアプローチが必要です。
短期的対策
助成制度の充実
- 23区共通助成制度の拡充
- 低所得世帯への特別支援
- 生活保護制度との連携強化
料金透明化の推進
- 火葬場運営コストの公開
- 料金設定根拠の明確化
- 定期的な経営状況報告
中長期的対策
公的火葬場の新設
現在の民間依存体制から脱却するため、23区による公的火葬場の新設を検討すべきです。用地確保や住民合意の課題はありますが、公共サービスの安定供給には不可欠です。
法制度の整備
- 墓地埋葬法の改正による監督権限強化
- 火葬場料金の届出制・認可制導入
- 非営利性確保のための法的措置
広域連携の推進
- 近隣自治体との火葬場相互利用
- 広域での火葬場整備計画
- 共同運営による効率化
他地域への波及リスクと全国的な課題
東京23区の問題は、決して東京だけの特殊な事例ではありません。全国各地で同様の問題が潜在的に存在している可能性があります。
民営火葬場の課題
全国には民営火葬場が多数存在し、その多くが地域の火葬需要を担っています。これらの施設でも、以下のようなリスクが考えられます。
- 経営方針の突然の変更
- 料金の一方的な値上げ
- サービス内容の変更・縮小
- 事業撤退や廃業
高齢化社会への対応
日本は超高齢化社会を迎え、今後火葬需要の急激な増加が予想されます。このような状況下で、民間企業への過度な依存は大きなリスクとなります。
予想される課題
- 火葬施設の処理能力不足
- 料金の高騰圧力
- サービス品質の格差拡大
市民ができること:声を上げ、制度改善を求める
この問題の解決には、行政や企業だけでなく、市民一人ひとりの関心と行動が重要です。
情報収集と理解
まずは問題の実態を正しく理解し、情報を共有することが大切です。火葬場の運営状況、料金体系、制度の仕組みについて関心を持ちましょう。
政治参加と要望活動
- 区議会議員への要望
- パブリックコメントへの参加
- 住民説明会への出席
- 選挙での意思表示
代替手段の検討
- 近隣自治体の火葬場利用の検討
- 生前準備による費用負担の軽減
- 互助会や保険商品の活用
国際比較:諸外国の火葬サービス事情
日本の火葬場問題を考える上で、諸外国の事例も参考になります。
韓国の事例
韓国では、火葬が急速に普及していますが、多くが公営施設として運営されています。料金も日本と比較して安価に設定されており、公的サービスとしての位置づけが明確です。
台湾の事例
台湾では、火葬場の運営を公的機関が行い、料金も低額に抑えられています。民間参入も認められていますが、厳格な規制のもとで運営されています。
これらの事例から、火葬サービスを公的サービスとして位置づけ、適切な規制の下で運営することの重要性が分かります。
まとめ:持続可能な葬送制度に向けて
東京23区の区民葬儀問題は、現代日本が直面する重要な社会問題の縮図と言えます。高齢化社会の進展、公共サービスの民営化、グローバル資本の参入など、複数の要因が絡み合って生じた複雑な問題です。
重要なポイント
問題の本質
- 火葬場の寡占状態による市場の失敗
- 公共的サービスの商業化の限界
- 法的規制の不備
緊急性
- 2026年3月からの制度変更
- 区民の経済負担増加
- 社会的弱者への影響
解決の方向性
- 公的関与の強化
- 法制度の整備
- 市民参加による制度改善
今後への期待
この問題の解決には時間がかかることが予想されますが、以下の点で前進が期待されます。
短期的改善
- 特別区長会による助成制度の実施
- 国による法制度整備の検討
- 火葬場運営の透明性向上
中長期的改革
- 公的火葬場の新設・拡充
- 広域連携による効率的運営
- 市民本位の葬送制度の確立
私たち一人ひとりができること
この問題は、決して他人事ではありません。誰もがいずれ直面する可能性のある課題です。だからこそ、今から関心を持ち、より良い制度づくりに参画していくことが重要です。
「生と死」は人間の普遍的なテーマです。その最後の局面で、経済的な理由により尊厳ある弔いが困難になることは、社会として避けなければなりません。今回の問題を機に、真に市民本位の葬送制度の構築に向けて、官民が協力して取り組んでいくことを強く期待します。
未来の世代に、安心して暮らせる社会を引き継ぐため、この問題への関心を持ち続け、建設的な議論と行動を続けていきましょう。私たち一人ひとりの声が、制度改善の原動力となるのです。
参考文献
[1] フジテレビ, 「東京23区の民間火葬場6つを経営している民間企業が2026年度から区民葬儀の取り扱いを取りやめると発表」, (2025年8月1日), https://www.fnn.jp/articles/-/911169
[2] 特別区長会, 「その他の活動」, https://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/sonota_kotsudo.html
[3] 日本経済新聞, 「東京の火葬料なぜ高い? 9万円で突出、全国平均1万円」, (2024年8月), https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD05AST0V00C24A8000000/
[4] 産経新聞, 「東京23区火葬料高騰、民営で9万円 中国資本傘下参入以降」, (2024年12月22日), https://www.sankei.com/article/20241222-PM2JFY7ZTRJT7KWSJUK23CPYJU/
[5] 東京都葬祭業協同組合, 「区民葬儀のご案内」, https://www.tosokyo.or.jp/keiyaku_sougi/kumin_sougi.php
[6] 広済堂ホールディングス, 「【東京博善】特別区区民葬儀の取扱い終了と火葬料金の改訂について」, (2025年8月1日), https://www.kosaido.co.jp/press/16246/
[7] 東京新聞, 「東京23区の火葬料がズバ抜けて高い地域事情 横浜の7倍超の施設も」, (2024年), https://www.tokyo-np.co.jp/article/324681
[8] 厚生労働省, 「火葬場の経営・管理について」事務連絡, (2022年11月24日), https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8658&dataType=1&pageNo=1
[9] 葬研(そうけん), 「東京博善の業績と利益、東京都における火葬場運営の事情まとめ」, https://souken.info/tokyo-hakuzen-mondaiten/
[10] 安心価格のいい葬儀, 「東京23区 火葬場併設斎場地図」, https://www.e-sougi.jp/kasouba/kasouba-map.html
[11] 東京博善株式会社, 公式サイト, https://www.tokyohakuzen.co.jp/
[12] coki, 「東京博善、区民葬から2026年3月末で撤退へ 公共インフラが営利化される日」, (2025年8月1日), https://coki.jp/article/column/56551/
[13] 葬儀の口コミ, 「火葬場の料金が都議選の争点に!注目が集まっているのはなぜ?」, https://soogi.jp/news/2129
[14] まいどなニュース, 「東京都23区内の火葬場…9カ所のうち、7カ所は民間運営」, https://maidonanews.jp/article/15097059
[15] 現代ビジネス, 「衝撃…!麻生グループ撤退した「東京の火葬場」を中国の実業家が買収していた」, https://gendai.media/articles/-/87425
タグ: 東京23区, 区民葬儀, 火葬場, 東京博善, 広済堂ホールディングス, 火葬料金, 中国資本, 特別区長会, 葬儀費用, 公共サービス
コメント
この記事へのトラックバックはありません。









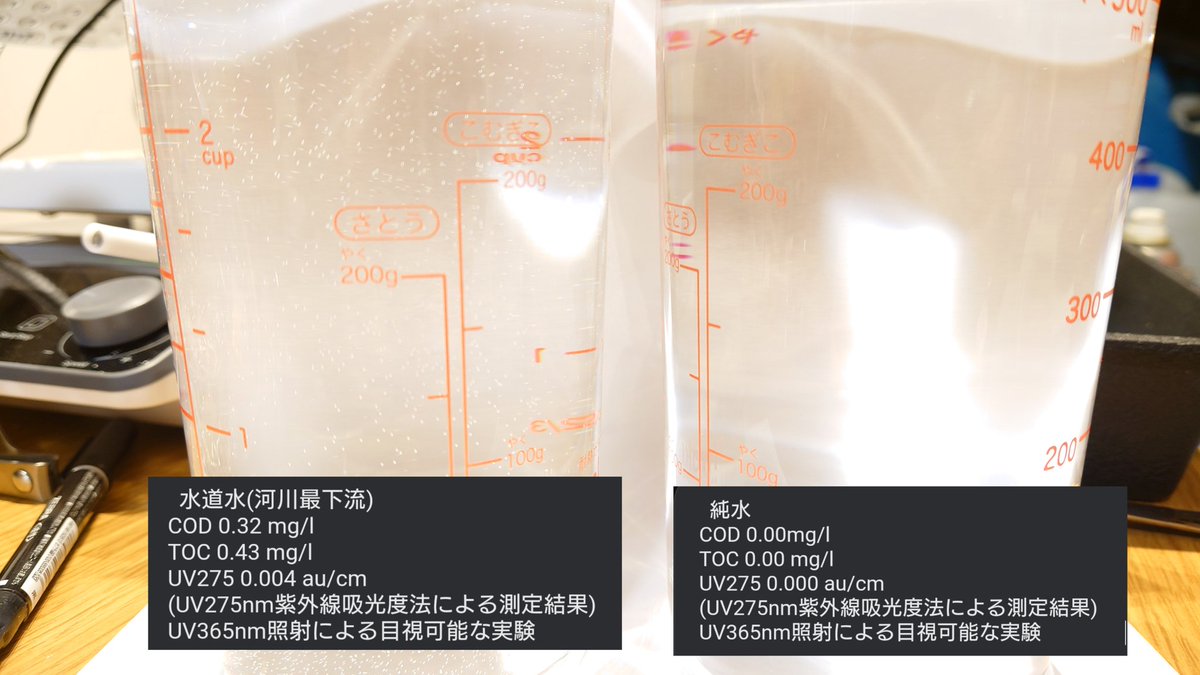

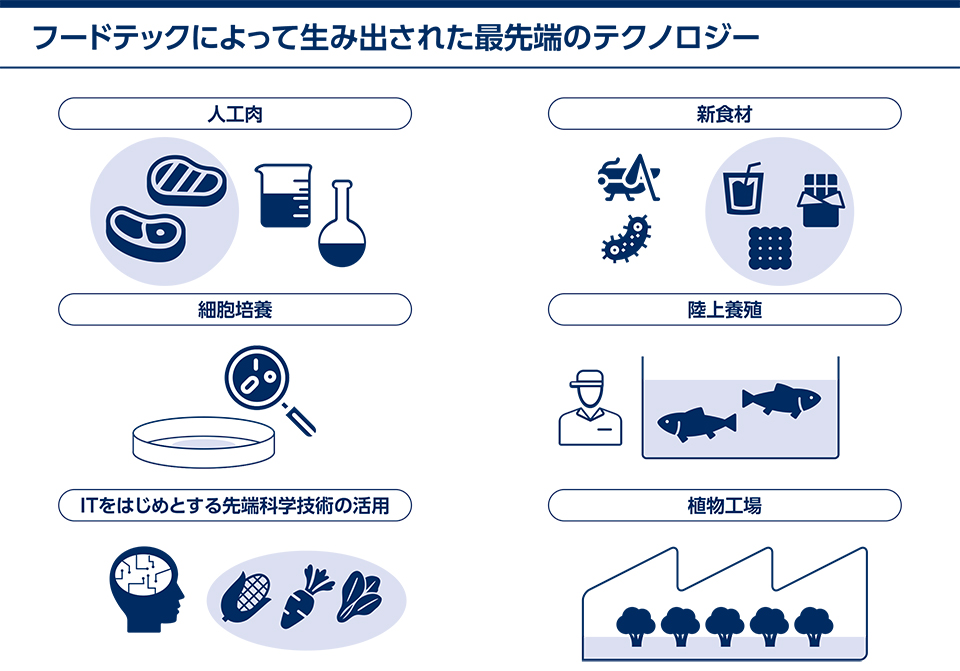
この記事へのコメントはありません。