10.30

DS918+のHDD換装とM.2キャッシュを増設
Synology DS918+
空容量が枯渇してきた。

そもそも、大部分をGoogle Driveに移行したので、今後、NASの容量は減らしていけると考えていた。そこにきて結構ショックなことが起きた。それは、Google SuiteがGoogle WorkSpaceに変わり、容量制限の付くことが発表された。容量の制限は個々のユーザー単位ではあるが、Googleに聞いたところ全体グループで容量はシェアできることらしい。今までは自分のグループだけで利用していたので問題なかったが、仕事としてお客様にも使っていただく様になったので、シェアをして容量を食い込ませるわけにはいかない。そこで、NASの容量増設となったわけだ。
現在のHDDの容量状況

4TBのHDDをRAID構成し、2本まで潰れても動作する様にしているので、実際に使える容量は10TB弱だ。これが現在、90%近くの使用率をうろついている。これはとても危険だ。何かあるとパンクするであろう。そこで、現在の費用対効果で考えられる投資をすることにした。
結論的には、4TBを2倍の8TBに変更する。すると簡単に言うと容量が2倍になるわけだ。20TBほど使えるよになるので、しばらくは大丈夫であろう。
もう一つ考えたことはパフォーマンス。特にアクセススピード。2倍の容量になるので、簡単に言うとファイルを呼び出すのに2倍弱かかるよになるであろう。メモリーで先読みするのでそこまでは遅くならないと思うが深刻ではある。そこで、HDDの手前でSSDを使って先読み、先書きをしてくれるM.2.SSDなるものをキャッシュとして使う。こう言うことまで機能として持っているSynology DS918+は優秀だ。
今回、RAID構成であることでコストを抑え以下のデバイスを用意する。
換装の方法
今回は、HDDの容量を大きするための換装作業と、HDDの内容を読み書きする際の効率を良くするためにSSDドライブによるキャッシュ設定を行う。先にも書いたが、HDDは8TBのHDDを4本用意し、1本ずつ交換することになる。既存の4本のHDDは、SynologyのSHRと言う独自のRAID形式である。通常のRAID5やRAIDXだと、全てのHDDを交換しないと容量は大きくならないが、特殊なRAID構成であり、HDDを入れ替えるたび、2本以上の交換で容量が増え始めてくれる。

ただし、今回は、全てのHDDを交換後にエリア拡張をしようと思います。初期段階での各HDDの容量が不均衡になるのを防ぎたいので。
M.2SSDキャッシュ

今回用意した、キャッシュ用のSSDです。一昔前は、HDDの手前でデータをキャッシュすると言えば、メモリーでやったものですが、現在では瞬電でも安心なSSDが使われています。
そこで今回は、512GBのSSDを2枚購入して、Read / Write用とした。

パリティの整合性チェック
今回の対応は容量のアップなのでHDDを1本ずつ交換していくしかない。その際に行われる処理が「修復」と「パリティチェック」だ。
修復とは、HDDを1本交換したことでRAID構成が壊れる。4本のHDDのうち、1つのファイルを3本のHDDに分割して保存し、1本のHDDにパリティ(整合性データ)を保存する。この仕組みによって、1本のHDDが壊れても他の3本で元のデータを維持することができる。という仕組みだ。
なので1本を交換するということは1本が壊れたのと同じ状態なので、交換後にデータの修復が行われ、その後、整合性のチェックが行われる。修復と整合性のチェックを同時にやることもできるであろうが、とにかく修復を急がないと、その間に他のHDDが壊れたら修復もできなくなるからね。だとしても整合性のチェックが済むまでは安心してはいられないが。。。
その、パリティチェックが、本数を交換するごとに時間がかかる様になってきた。これはどういう仕組みなのであろうか?
NAS全体の容量を見ていると、2本まで交換した時点では全体容量がさほど増えていないが、3本目の交換後は修復後の全体容量が一気に増えてくる。そのためHDD全体のチェックに時間がかかっているの「かも」しれない。ちょっとこの辺りはわからないが、仕方がないなあ〜。
3本目のHDD換装完了
この時点で、容量が大きく使える様になった。本来、2本目でも大きく使えるよになるが、それはマニュアルで変更する必要がある。3本目が完了すると自動で拡張される様だ。

4本目の最終HDD換装作業
作業自体はすぐに完了したが、4本目のパリティーチェックに物凄い時間を要している。3日かかっても完了していない。
そして、やっとこ4日目にして完了を迎えた。現在までの拡張は12TBあまりの容量だったのが18TBまで拡張された。最後の1本入れ替え後の容量は、自身で拡張する必要がある様だ。
完了!
その手順を実施することで、22TB弱の容量、つまり以前より10TB拡張できたことになる。しかもRAID構成なので1本のディスクが壊れてもデータは破損せず、更にR/Wキャッシュ用にSSDも追加したのでデータアクセスのレスポンスが向上した。その分、CPU使用率も高くなったが。しばらくは、この状態で運用を継続できる様になった。


コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。






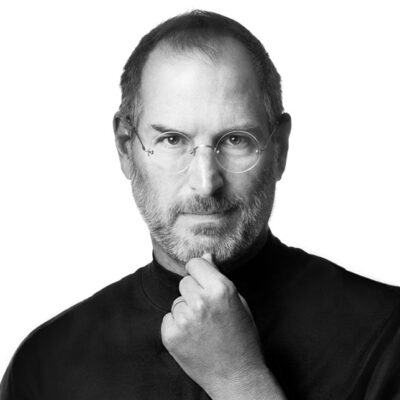

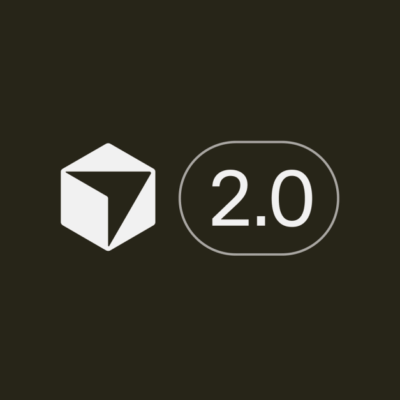

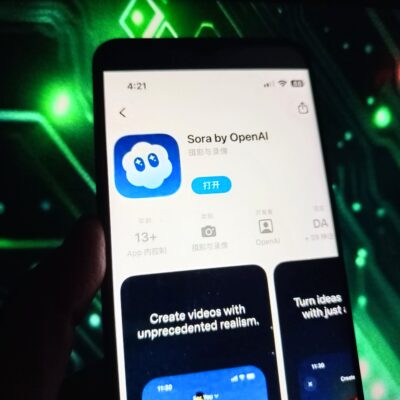
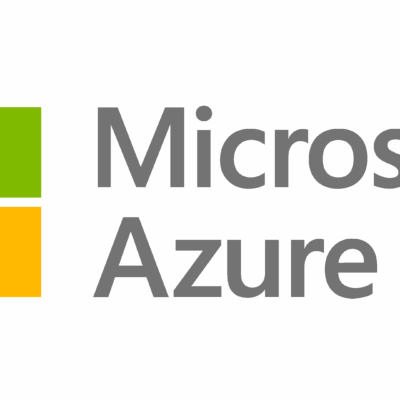
この記事へのコメントはありません。