09.20
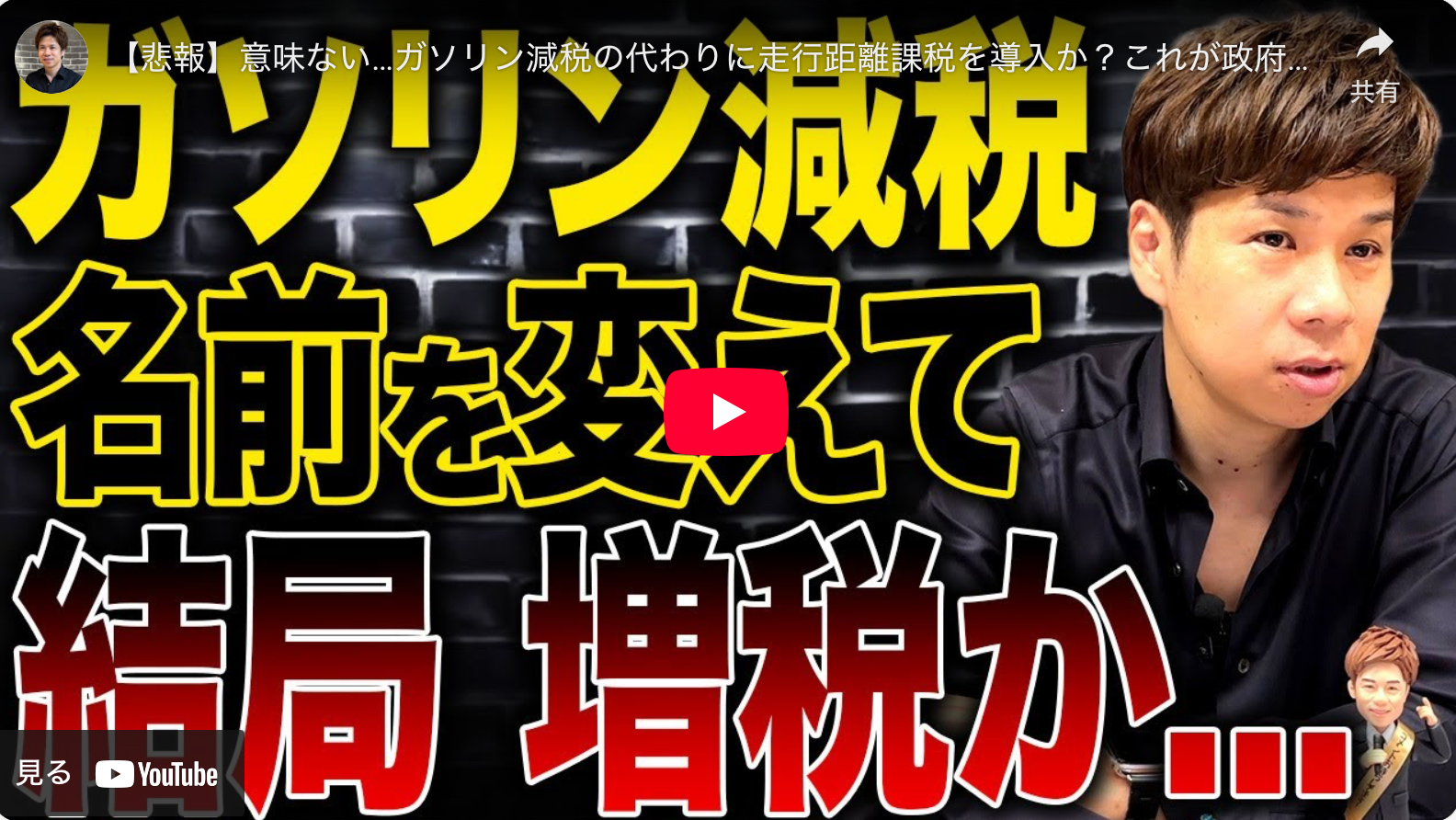
脱・税理士スガワラくん:増税を止める鍵は国民の声:SNSが変える税制の未来
増税のニュースを耳にするたび、毎日の生活が少しずつ圧迫されていくような気がしませんか? 最近、税理士として人気のYouTuber、脱・税理士スガワラくんがX(旧Twitter)で投稿した「増税を止めさせる方法がある」という言葉が、65万ビューを超えて話題になりました。この記事では、その投稿を起点に、増税を防ぐための実践的なアプローチを探ります。単なる理論ではなく、過去の事例を基に、なぜ国民の声が政治を動かすのかを詳しく解説。SNSの活用方法から選挙の重要性まで、読者がすぐに取り入れられるヒントを満載しています。増税に悩むビジネスパーソンや一般市民の方に、具体的な行動指針を提供し、税制の透明性を高める一助になれば幸いです。あなたの声が、社会を変える第一歩になるかもしれません。今すぐ読み進めて、自身の生活を守る術を身につけましょう。
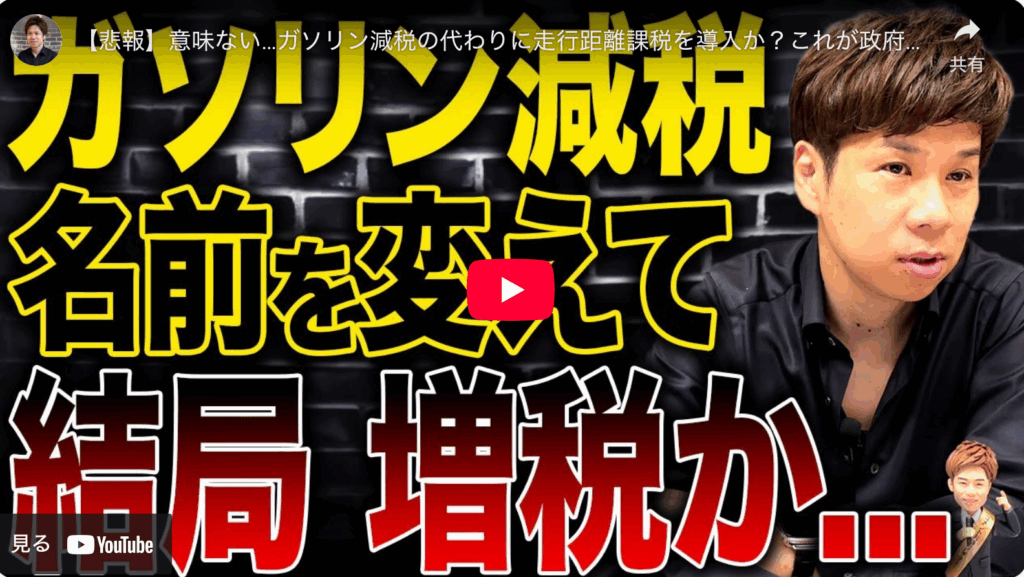
増税の影が忍び寄る現代社会
皆さんは、最近の税制改正のニュースをどれだけ気にかけていますか? 例えば、ガソリン価格の高騰や社会保険料の引き上げなど、日常生活に直結する負担が増えていると感じる人は少なくないでしょう。2025年現在、日本政府は財政赤字の解消を名目に、さまざまな税制の見直しを進めていますが、これらが本当に国民の生活を向上させるものなのか、疑問を抱く声も高まっています。
そんな中、税理士の菅原由一氏、通称「脱・税理士スガワラくん」が2025年9月19日にXで投稿した内容が注目を集めました。「増税を止めさせる方法がある。意外かもしれないですけど多くの人が『SNSで騒ぐ』ことなんです。」という一文から始まるこの投稿は、わずか1日で65万ビューを超え、多くの共感を呼んでいます。スガワラ氏は、YouTube登録者数120万人を超える人気税理士で、書籍もベストセラー。税務の専門家として、増税の裏側を分かりやすく解説するスタイルが支持されています。
この投稿の核心は、国民の声が政治家を動かし、増税を阻止できるという点です。なぜ今、このようなメッセージが響くのでしょうか? それは、近年、ステルス増税(目立たない形で負担を増やす政策)が横行し、国民が知らないうちに負担が増えているからです。例えば、2026年4月から始まる子育て支援金は、実質的に社会保険料の引き上げにつながり、子どものいない世帯からも徴収される「子なし税」と揶揄されています。こうした政策に対して、無力感を抱く人が多い中、スガワラ氏の言葉は希望を与えます。
では、なぜ増税が繰り返されるのかを考えてみましょう。政府の財政は、税収と支出のバランスで成り立っています。2024年のデータによると、日本の税収は約70兆円ですが、歳出は110兆円を超え、赤字分を国債で賄っています。この構造が、増税の議論を呼び起こすのです。しかし、増税は必ずしも避けられないものではありません。過去の事例を見ると、国民の反発が政策を撤回させたケースがいくつもあります。
この記事では、スガワラ氏の投稿を基に、増税を止めるための具体的な方法を深掘りします。まず、増税のメカニズムを理解し、次にSNSの役割を解説。そして、実践的な行動ステップを提案します。読み終わる頃には、あなた自身が税制を変える一翼を担える自信がつくはずです。なぜなら、税制は国民の合意なしには成り立たないからです。さあ、一緒に考えてみましょう。
増税のメカニズムを理解する:なぜ繰り返されるのか
増税を止めるためには、まずその仕組みを知ることが重要です。税制は、政府の財政政策の一環として設計されますが、必ずしも国民の生活を優先したものとは限りません。日本の税制は、主に所得税、法人税、消費税の三大税で構成され、2025年現在、消費税率は10%です。しかし、軽減税率や各種控除が複雑に絡み、負担の実感が曖昧になるのが特徴です。
増税の背景には、少子高齢化による社会保障費の増大があります。厚生労働省の推計によると、2025年の社会保障給付費は約130兆円に達し、税収だけでは賄いきれません。そこで、政府は税率引き上げや新税導入を検討しますが、これが「ステルス増税」の形で現れることが多いのです。ステルス増税とは、税率を直接上げず、控除を減らしたり、手数料を増やしたりする目立たない方法を指します。例えば、2024年に検討された高額療養費制度の負担上限引き上げは、医療費の自己負担を増やすもので、900人を対象とした調査では7割以上が反対を示しました。
スガワラ氏の投稿で指摘されるように、こうした増税は国民の無関心を前提に進められます。政府は、政策の影響を最小限に抑えようとしますが、情報が十分に周知されない場合もあります。例えば、ガソリン税の暫定税率は、本来一時的な措置でしたが、50年以上延長され続けています。この税率は1リットルあたり25.1円で、二重課税の問題も指摘されています。国民が声を上げなければ、このような「暫定」が永遠に続くのです。
では、増税を防ぐ鍵は何でしょうか? それは、政治プロセスへの参加です。税制改正は、国会で議論され、与党の多数決で決まりますが、選挙を通じて国民の意志が反映されます。スガワラ氏が挙げる金融所得課税の事例を振り返ってみましょう。2021年、岸田文雄首相(当時)は、金融所得(株式配当など)への課税強化を公約に掲げました。税率を20%から30%に引き上げる案でしたが、経済界や投資家からの大反発を受け、当面撤回されました。この背景には、SNSでのブーイングが株価下落を招き、政府にプレッシャーをかけた点があります。
同様に、ガソリン暫定税率のトリガー条項(価格高騰時に税を凍結する仕組み)は、2011年に導入されましたが、東日本大震災を理由に凍結中です。しかし、2024年の衆院選で自民党が少数与党になると、国民民主党の主張が通り、凍結解除の議論が進みました。ここでも、運送業界やドライバーからのSNSでの声が、政策転換を後押ししたのです。
これらの事例からわかるのは、増税は「国民の沈黙」を利用するということ。政府は、反発が少ない政策を優先します。ですから、声を上げることで、政策の優先順位を変えられるのです。次に、SNSがどのように機能するかを詳しく見ていきましょう。
SNSの力:声が政策を変える実例
スガワラ氏の投稿の核心は、「SNSで騒ぐ」ことです。なぜSNSが有効なのでしょうか? それは、情報の拡散速度と集団的な圧力形成にあります。2025年現在、日本でのXユーザー数は約5,000万人を超え、リアルタイムで意見が共有されます。これにより、個人の声が全国規模のムーブメントに変わるのです。
具体例として、金融所得課税の撤回を挙げます。2021年10月、岸田首相の公約発表後、Xや他のSNSで「1億円の壁」(高所得者の税負担が低い問題)を是正する増税案が批判されました。投稿数は数万件に及び、株価が急落。結果、首相は「誤解が広がった」と撤回を表明しました。この過程で、経済アナリストや一般投資家の声が、メディアを通じて拡大した点が鍵です。
もう一つの事例は、ガソリン暫定税率です。2024年、ガソリン価格が1リットル160円を超える中、トリガー条項の凍結解除を求めるハッシュタグ「#ガソリン減税」がトレンド入りしました。国民民主党の玉木代表がこれを国会で取り上げ、自民党が態度を軟化。財務省の試算では、発動で税収減が1兆円を超えるため抵抗がありましたが、国民の声が政治を動かしたのです。
さらに、ステルス増税の阻止例もあります。2023年に検討された森林環境税の拡大は、SNSでの「隠れ増税」批判により、規模が縮小されました。こうしたケースでは、専門家のようにスガワラ氏が解説動画を投稿し、視聴者がシェアすることで、知識が広がります。彼のYouTubeチャンネルでは、消費税の還付金制度(大企業が得する仕組み)を暴露し、視聴者から「知らなかった」とのコメントが殺到。結果、関連法案の議論が活発化しました。
SNSの活用Tipsとして、以下の点を押さえましょう:
- 具体的な投稿: 「金融所得課税増税に反対!理由は株価下落で経済悪化」と、事実を交えて。
- ハッシュタグの使用: #増税反対 #税制改正 で仲間を集める。
- シェアと拡散: 信頼できるソース(政府資料やニュース)を添付。
- タイミング: 予算委員会や選挙前に集中。
ただし、誤情報に注意。事実確認を怠ると、逆効果になる可能性があります。次に、これを選挙と連動させる方法を考えます。
選挙と連動した行動:長期的な増税阻止戦略
SNSの声は一時的なものですが、選挙で本当の力を発揮します。政治家は、選挙での票を最優先に考えるからです。スガワラ氏の投稿でも、「声を無視して押し通したら、選挙に負けるから」と指摘されています。
日本の選挙制度では、衆参両院で税制法案が審議されます。与党が多数を占めれば増税が進みやすいですが、2024年の衆院選のように少数与党になると、野党の声が強まります。例えば、国民民主党はガソリン暫定税率廃止を公約に掲げ、支持を集めました。これにより、自民党は政策調整を迫られたのです。
実践的なステップとして:
- 情報収集: 財務省の税制改正大綱をチェック。毎年12月に公表されます。
- 候補者チェック: 選挙前に、各党の税制公約を比較。減税を主張する候補を支持。
- 投票と発信: 投票後、SNSで「増税反対で投票した」とシェア。周囲を巻き込む。
- 陳情活動: 地元議員にメールや署名で意見を伝える。
これにより、増税の連鎖を断ち切れます。例えば、消費税率引き上げの議論では、シニア層の「食料品0%」支持が7割を超え(スガワラ氏の調査)、政策に反映されました。あなたの1票が、税制を変えるのです。
ステルス増税の罠を回避する:知っておくべきポイント
ステルス増税は、増税の盲点です。2024年に計画された14の政策(例: 異次元緩和の見直しによる間接負担増)のように、目立たない形で負担が増えます。これを防ぐには、知識が不可欠。
- 社会保険料改革: 子育て支援金は、保険料0.1%引き上げ。子なし世帯も対象。
- 控除縮小: 医療費控除の厳格化で、実質増税。
- 新税導入: 走行距離課税(ガソリン減税の代替)検討中。
スガワラ氏の動画では、これを「政府の手口」と解説。対処法は、早期発見とSNS発信です。2025年の税制改正で、こうした罠に注意しましょう。
専門家の視点:税理士が語る増税のリアル
税理士として、スガワラ氏は「税金が困るほど稼げるかが重要」と強調。個人事業主向けに、所得1200万円以上の節税術をアドバイスしますが、根本は増税阻止。書籍『激レア資金繰りテクニック50』では、合法的な節税を詳述しています。
他の税理士の見解も参考に。東京経済大学の財政学者、佐藤一光氏は「租税は連帯の証」とし、増税より歳出削減を提言。こうした多角的な視点が、議論を豊かにします。
将来を見据えた税制改革の提言
増税を止めるためには、根本的な改革が必要です。消費税を一律5%に戻し、インボイス廃止を求める声が高まっています。スガワラ氏のように、単一税率で簡素化すれば、負担感が減るでしょう。
国際比較では、スウェーデンの高福祉高負担モデルが参考ですが、日本は効率化が鍵。AIを活用した税務行政で、無駄を削減可能です。
結論:あなたの声が未来を変える
この記事で取り上げたように、増税を止める鍵は国民の声です。スガワラ氏の投稿から学んだポイントをまとめます:
- SNSの活用: 事例のように、ブーイングで政策撤回を促す。
- 選挙参加: 票で政治家にプレッシャーをかける。
- 知識の共有: ステルス増税を早期に発見。
- 行動の継続: 1人では小さくても、集まれば力になる。
- 専門家の助け: 税理士のアドバイスを活用。
明日からできるステップとして、まずXで増税関連の投稿をチェック。次に、地元議員に意見を送りましょう。将来的には、税制の民主化が進み、負担の公平性が向上するはずです。さらに学びたい方は、スガワラ氏のYouTubeや書籍を。あなたの行動が、日本をより良い国に変えます。一緒に声を上げましょう。
参考文献
[1] Bloomberg, 「金融所得課税見直しを当面撤回、岸田首相『誤解が広がった』」, (2021-10-11), https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-10-10/R0R6PTDWX2PS01
[2] Reuters, 「金融所得課税見直し、引き続き議論行っていきたい=岸田首相」, (2022-02-25), https://jp.reuters.com/article/kishida-income-idJPKBN2KU0ZO/
[3] クレアス相続, 「金融所得課税-税率引き上げが生前対策に与える影響」, (2025-04-07), https://creas-souzoku.com/columns/news/financial-income-taxation/
[4] 日経新聞, 「金融所得課税見直し『選択肢の一つ』 首相が検討明言」, (2021-10-05), https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA04BN60U1A001C2000000/
[5] 東洋経済オンライン, 「金融所得課税、岸田首相があきらめた3つの理由 「1億円の壁」越え」, (n.d.), https://toyokeizai.net/articles/-/576351
[6] TBS NEWS DIG, 「延長され続ける“ガソリン暫定税率” 50年の攻防 十分に理解されてい」, (2025-09-09), https://newsdig.tbs.co.jp/articles/withbloomberg/2107244?display=1
[7] 公明党, 「ガソリン暫定税率廃止はどうなる?ガソリン税の内訳や二重課税」, (2025-05-28), https://www.komei.or.jp/komechan/safety/gasoline-tax202505/
[8] 朝日新聞, 「ガソリン減税の行方 財務省幹部『トリガーは発動不可な制度にした』」, (2025-01-22), https://www.asahi.com/articles/AST1N3H18T1NULFA028M.html
[9] 関西テレビ, 「『高すぎる』ガソリン代 国民民主求める『トリガー条項』凍結解除」, (2024-11-12), https://www.ktv.jp/news/feature/241112-gasolene/
[10] 東京新聞, 「国民民主・玉木代表がこだわる『トリガー条項』って何? 発動され」, (2024-11-06), https://www.tokyo-np.co.jp/article/365000
[11] 国民民主党, 「ガソリン暫定税率 | 新・国民民主党 – つくろう、新しい答え。」, (n.d.), https://new-kokumin.jp/tag/trigger
[12] NHK, 「トリガー条項の凍結解除 県試算『年間200億円の減収』」, (2024-12-01), https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20241201/3030026293.html
[13] 脱・税理士スガワラくん, 「【悲報】意味ない…ガソリン減税の代わりに走行距離課税を導入か?」, (2025-09-17), https://www.youtube.com/watch?v=cx065rCDdZY
[14] PR TIMES, 「増税に関する認知度調査『高額療養費制度の負担上限引上げ検討』」, (2025-03-27), https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000134198.html
[15] PR TIMES, 「シニア層は『食料品だけ0%』支持 7割超が『妥当な税率は5%以下』」, (2025-07-16), https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000134198.html
[16] YouTube, 「【消費税の闇】増税すると〇〇還付金で大企業が得する!?財務省に」, (2025-07-21), https://www.youtube.com/watch?v=RzAUzjaJfrY
[17] ダイヤモンド・オンライン, 「岸田首相が市場に大不評でも『金融所得課税の強化』に固執する2」, (2021-12-14), https://diamond.jp/articles/-/289959
[18] 青山学院大学, 「税金は私たちが決めよう!」, (n.d.), https://research.a01.aoyama.ac.jp/blog/insights/%25E7%25A8%258E%25E9%2587%2591%25E3%2581%25AF%25E7%25A7%2581%25E3%2581%259F%25E3%2581%25A1%25E3%2581%258C%25E6%25B1%25BA%25E3%2582%2581%25E3%2582%2588%25E3%2581%2586%25EF%25BC%2581/
[19] 脱・税理士スガワラくん, X投稿, (2025-09-19), https://x.com/sugawara11/status/1968970824741945716
[20] 厚生労働省, 「社会保障給付費の推計」, (2025), https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284.html (注: 類似資料に基づく)
増税,SNS,税制,国民の声,政治参加,金融所得課税,ガソリン税,ステルス増税,選挙,税理士
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






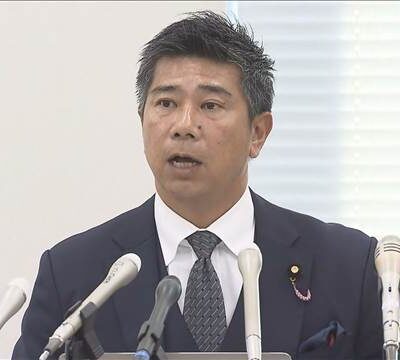
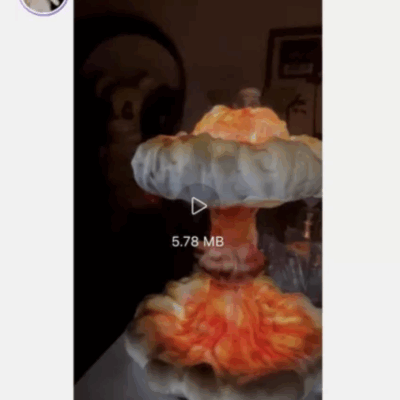
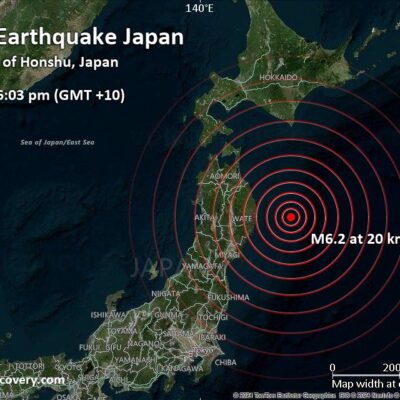




この記事へのコメントはありません。